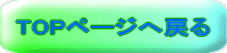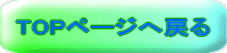

人が生きていくために、酸素は欠かすことができません。この酸素を体内に取り込む働きをしているのが呼吸器と言われる器官です。鼻や口からつながった喉頭、気管支、そして肺が呼吸器です。このページでは、酸素を取り込み、二酸化炭素を出す呼吸器の仕組みなどを紹介します。
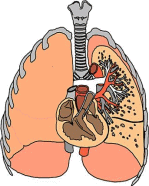
【呼吸器の概略】
呼吸によって酸素を取り込んでいることはみなさんご存知でしょう。酸素を取り込みこの酸素が血液(赤血球)にひっついて、心臓の働きによって運ばれ、あらゆる臓器の細胞に届けられているのです。こちらのページで、体循環と肺循環を説明していますので、一緒に見ていただきたいのですが、全身の細胞で酸素が使われ二酸化炭素を多く含んだ血液は、静脈を通り右の心臓に戻ってきます。そして右の心臓から肺に送られます。肺でこれから説明するガス交換が行われ、酸素を多く含んだ動脈血となり、左の心臓へ戻り、そして再び全身の細胞に血液が送られ酸素が届けられるわけです。
【空気の通り道】
呼吸器系は、口腔や鼻腔などの空気の進入口から始まり、咽頭、喉頭、そして気管へと続きます。気管は左右に分岐した後、気管支となり2分岐を繰りかえして、最後に肺胞と言う場所につながります。一般に何の抵抗もなく空気は流れ込みますが、この気管支の表面には、外部からの異物や細菌の進入を防ぐための多くの機構があり、正常であっても分泌物を口腔内へと徐々に送り出して絶えず、気管内を清潔に保つ働きがあるのです。仮にここに炎症が生じると、その分泌物が痰として排出されるわけです。また咳反射は、この異物などを一気に喉の方へ押し出す働きをしており、咳によって清潔を保っているわけです。咳はイヤなものですが、体が求める大切な反射であることは理解しておいてください。
【呼吸に必要な神経と運動】
みなさん、深呼吸をしながら、二つのことを考えてみてください。
一つは、息をするという動作が、意識して行うことができる反面、意識しなくても、たとえ寝ていても呼吸ができると言うことです。つまり呼吸をするための命令は延髄と言われる脳の中枢神経と大脳による命令の二重支配を受けているのです。ですから意識して息を止めたり、逆に深呼吸運動などができ、また意識しなくても寝ていても呼吸できるわけです。しかし麻酔などによって呼吸中枢も麻痺すると呼吸が止まってしまうのです。
もう一つは、息をするために動いている筋肉です。肺はそれ自体は膨らんだり縮んだりする力はありません。周囲の入れ物(肋骨や筋肉、そして横隔膜に囲まれた)と肺との間が陰圧になっているため、周囲の入れ物が膨らむと引っ張られる形で膨らみ、入れ物が縮むと肺も縮むのです。ですから息をしているのは、肺ではなく、肋骨や肋間筋、横隔膜であると言うことになります。
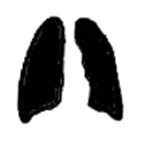
【酸素を取り込むガス交換】
それでは、吸い込まれた空気からどうやって必要とする酸素を取り込んでいるのでしょう?
それは、肺胞と言う場所で行われています。肺胞には、右の心臓から送られてくる血液が流れてきます。この血液は全身の細胞が酸素を使い、二酸化炭素を多く含んだいわゆる汚れた血液です。そしてこの血液と吸い込んだ空気は肺胞の膜を通してガス交換します。つまり血液中から二酸化炭素を取り出し、空気中の酸素は血液中に入り、いわゆるきれいな血液となるわけです。(下のアニメの赤玉は二酸化炭素、青玉は酸素です。薄いピンクの部分が肺の中の血管で、薄い青の部分が肺胞で気管支につながっています。)
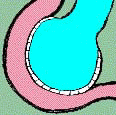

【正常呼吸のための条件】
このように、脳からの呼吸の命令が確実に伝わり、そして肺を包んでいる肋骨や肋間筋肉、そして横隔膜などの胸郭の運動が障害なく行われ、また気管支や肺に障害がなく、空気がスムーズに通り、順調に肺胞でガス交換が行われている場合が、正常の呼吸なのです。
では、呼吸が正常に行われるために必要なことをもう一度並べてみましょう。
- 空気の通り道である、口腔・鼻腔・咽頭・喉頭そして気管に障害物がないこと
- 吸い込まれた空気と肺へ流れてくる血液の間で行われるガス交換に支障がないこと
- 呼吸をするための胸郭(肋骨や肋間筋肉、横隔膜など)の障害がないこと
- 肺へ流れてくる血液、そして肺から流れ出る血液に問題がないこと
- 肺そのものが、損傷したり、堅くなったりしないこと
- 脳からの呼吸の命令が的確であること
以上が、呼吸を正常に行うための条件といえるでしょう。
逆に、それぞれを障害する疾患を番号にあわせて提示してみましょう。
- お餅をつまらせたりする気道内異物が有名で、いわゆる窒息です。気管支喘息発作もこれに含まれ、気管支が収縮してしまい空気、特に呼気が通りにくくなります。
- 心不全による肺水腫(心臓が順調に働かないため肺に血液が貯まり肺の組織内に水分があふれてくる状態)や肺炎によって肺胞の壁に障害が生じたときが典型的です。
- 肋骨骨折や胸部の筋肉を痛めて呼吸しても痛いときは、息も十分にできません。また気胸と言って本来陰圧である胸郭と肺の間に空気が貯まっても同様です。また希な例としては筋肉疾患やフグ中毒などによって呼吸をするための筋肉が動かない場合もこれに当たります。
- 肺動脈(右の心臓から肺へ血液が送られる血管)に血栓などがつまってしまう肺塞栓症が有名です。
- 交通事故で肺を損傷したり、癌によって肺組織が破壊されれば当然呼吸に異常を来たします。
- 脳の機能が低下して呼吸することさえ命令できなくなった状態がわかりやすいですが、逆に精神の緊張により過換気と言って呼吸を深く速くしすぎる状態も同様にこの障害と考えていいでしょう。

いかがでしたか?少しは呼吸について理解していただけたでしょうか?
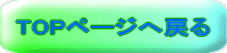


![]()
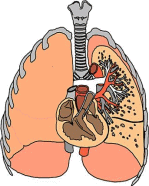
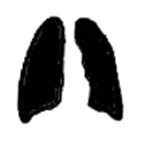
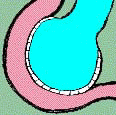
![]()
![]()