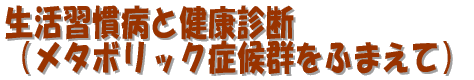
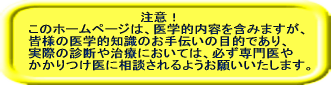
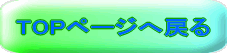
以下の関係から見たい項目を選んで下さい。

以下の関係から見たい項目を選んで下さい。
一昔前まで成人病と言われていた生活習慣病。確かに成人病より生活習慣病の方が理解しやすいと思います。一般には成人になって発症しやすい生活習慣が発症要因に深く関わっているような疾患群を生活習慣病と称します。成人病という概念では癌も含む場合がありましたが、生活習慣病としては癌は含めずに考えます。
高血圧、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症、脂肪肝について取り上げて説明を加えていますが、必要に応じて心筋梗塞や脳卒中などの疾患についても説明を加えていきます。まず生活習慣病の大きな特徴を二つあげます。
・自覚症状がほとんどない
・放置することにより恐ろしい合併症を併発する可能性が高い
ほとんどの生活習慣病は無自覚無症状が多いです。もちろん症状が現れる場合もありますが、初期にはほとんどの場合、疲れていたからとか体調が悪いと言った言葉ですまされるようなものなのです。そしてこう言った生活習慣病は、徐々に体をむしばみ、やがて恐ろしい心筋梗塞や脳卒中につながっていくのです。以上の二つは、皆様ご存じでしょう。しかしだからと言って対処してみえる方は本当に少ないのが事実です。どうしてでしょうか?それは、実感がないからなのでしょう。痛みを伴ったり、苦しければ誰でも対処しますが、無自覚無症状ではわかっていても対処できません。また始めても長続きしないようです。中には「健診で何も言われてなかった人でも心筋梗塞になった人もいる」と言って気にしないように努める方もみえます。確かにそう言う人もみえますが、明らかに高血圧、高脂血症、糖尿病などを持っている人の方が発症率は数倍高いのです。例えば心筋梗塞の場合、高血圧、高脂血症、糖尿病、それに喫煙、肥満、ストレスなどを加えて医学的には危険因子と言って、幾つ存在するかを注意しています。
現代社会におけるストレスも、生活習慣病の大きな原因です。
生活習慣病は、体質的に持ってみえる疾患のみでなく、明らかに生活習慣的要因が強いものです。ですから対策として生活習慣の代表である食事と運動は避けて通ることができません。食事や運動に関して厳しいことをいきなり言うつもりはありません。しかし「私は、間食もしないし、食事量も気をつけてますから・・」と言いつつ、缶コーヒーを日に2~3本飲まれていたり、決まった食事以外に毎晩アルコールをとられる方もみえます。また運動というと、「私は仕事で汗をかきますから・・」と荷物の積みおろし作業をあげられる方もみえます。しかしここで言う運動はいわゆるエアロビクスゾーンに入った持続した有酸素運動のことです。また主婦の方が「一日中動いてますから」と言われても、これは運動とはならないのです。このように、対処するためには正しい対処方法を知る必要もあります。糖尿病で薦める食事や運動療法は、全てに共通しています。(糖尿病の項目参照)是非生活習慣を改め生活習慣病対策の一歩を進めて下さい。

さて糖尿病というのは、尿に糖が出る病気と書きますが、本体はインスリンが不足したり出なかったりする内分泌と言われる分野の病気なのです。1型と2型糖尿病と分けますが、日本人の多くは2型で、以前言われていたインスリン非依存型糖尿病と言うものです。インスリンは血液中の糖を筋肉や肝臓などの細胞が栄養分として利用するのに不可欠な物です。インスリンの分泌によって当が利用され、その結果として血糖値は正常まで下がってくるわけです。もしインスリンの分泌が悪いと、しばらくの間血液中の糖分は高いまま存在し、ようやく徐々に分泌されたインスリンによって血糖値が正常に戻った頃には、次の食事によって再び血糖が上昇し、結果としてほとんどの時間高血糖が続くことになります。これが多くの日本人の糖尿病のパターンです。そしてこの体質は遺伝されます。遺伝された体質の方に過食、不規則な食事、運動不足、ストレスなどが加わって徐々にインスリン分泌が悪化して発症するのです。またインスリン抵抗性というものがあります。以前は西欧人に多いタイプとして理解されてきましたが、近年は食生活も昔の日本とは異なり、更に慢性的な運動不足などから、このインスリン抵抗性が増えています。インスリンが分泌されても、抵抗性があるため、本来の働きを示してくれない。つまり血糖が下がらないのです。更に過剰のインスリンは高インスリン血症と言って、メタボリック症候群ではその病態を更に悪い方に進める作用があります。
インスリン分泌不全とインスリン抵抗性、これが糖尿病の本体と言えます。
食事やアルコールを楽しむことも大切です。
しかし、個人個人の制限について考えてください。では、どうしたらよいのでしょうか?まずインスリンの分泌が悪くなった理由を取り除くことです。肥満傾向の人は食事療法をしてダイエットをする。これのみで血糖が正常化する方はたくさんみえます。そして正しい食事療法です。また運動療法も大切です。それでも血糖の良好なコントロールができない人は、お薬やインスリン注射を用います。詳細は上記で示したホームページを参照していただきたいのですが、ここでは、最も陥りやすい間違いや注意すべき点をまとめます。
1:多少の食事療法をしたから、それで満足している人
2:食事療法は行わず、運動しているから良いと思っている人
3:医師に相談せず民間療法にのみ頼って、それで満足している人
1番目の意味は、糖尿病というと食事というイメージがあり、指摘されるととりあえず食事を多少制限される方が多いようです。そして本人にとってはすごくがんばっているように感じます。ですから何となく対処できているような気になります。しかし実際の指導にそって行うものとは異なり、ほとんどの場合無意味な食事療法をされていることが多く、しかもそのうち徐々に元に戻っていってしまいます。しかも人によっては食事のみではコントロールが不可能な場合もあります。2番目の意味は、運動を過信している方です。毎日歩いているからとか、ゴルフの練習しているからなどと言って食事療法は考えない人です。ちなみに缶コーヒー1本分を運動で消費するためにどの程度の運動が必要かご存じでしょうか?缶コーヒー1本で約100~250カロリー(無糖は除く)あります。ジョッギングなら約30分、なわとびなら約15分、平泳ぎなら約20分必要となります。運動はインスリンの反応や活性を高める意味で必要ですが、けっしてカロリーを消費するためのものではありません。不思議と運動して汗をかくとその後多少食べてもかまわないような錯覚に陥ることは事実です。しかしこれは特に注意が必要なのです。3番目は、医療機関へ行くことが面倒、嫌い、恐いなどの理由で受診せず、近くの薬局や知人から薦められた民間療法のみを行う人です。民間療法を否定しているのではありません。行うことは害がなければかまわないでしょう。しかし自分の糖尿病の状態も知らず、民間療法のみをやっているから大丈夫と言うはずがありません。
よく噛んで食べる。これも大切なことです。
以上の点から糖尿病と指摘されたなら行って欲しい点をまとめます。
1:必ず自分の糖尿病の程度や状態を医師に診てもらい、一度は指導を受ける。
2:運動や食事療法はただやるのではなく、効果的な正しい指導の元に行う。
3:医師に自分の希望や生活上の規制を話す。例えばどうしても内服は避けたいとか、運動は仕事上限度があるなど・・。
糖尿病は一度診断されると完全に治ると言うことはありません。しかしコントロールする事は可能です。この意味が理解できるように糖尿病についてまずは知識を増やして下さい。
高血圧という疾患を知らない人はいないでしょう。しかし高血圧という状態がどう言った状態で、どう言うことを引き起こすかを知っている人は少ないと思います。ここでは、高血圧とはどう言った状態で、放置するとなぜいけないのか? そして高血圧の治療の基本についてお話しします。
血圧を決めている因子が何かご存じでしょうか? オームの法則による電圧=電流×抵抗と同じで、血圧=血液の流れ×血管の抵抗なのです。例えば出血して血液量が減ると血圧は下がります。逆にどんどん点滴すれば血圧は上がります。また安静にすると血管抵抗が下がり血圧は下がりますが、緊張すると上がります。それでは、高血圧の人は何が原因なのでしょうか? 全ての人が同じとは限りませんが、多くは血管抵抗の上昇です。歳をとって動脈硬化、つまり血管が固くなり弾力がなくなると血圧は上昇します。しかしそうでなくても血管には平滑筋と言う筋肉があり一定の抵抗を作り出しています。そして高血圧の方の多くは、この抵抗が上がるような要因があるのです。血管抵抗が上がり結果として血圧が高いとどうなるのでしょうか?いつも通常より高い圧力が血管の内側にかかることになります。それが数年数十年と続くと徐々に血管の内側に破綻が生じます。そしていつの間にかそこが変化して、時に血管の内側が狭窄したり、あるいは閉塞(つまってしまう)したり、あるいは固くなった血管が破れてしまうのです。これらが心臓の筋肉へ血液を送っている冠動脈に生じると心筋梗塞や狭心症であり、また脳の血管で生じれば脳卒中と言うことになります。更に腎臓との関係は複雑ですが、腎臓の血管の抵抗が上がることによって、更に血圧を上げるような物質を腎臓は分泌するのです。結果としてますます血圧が上昇してしまいます。
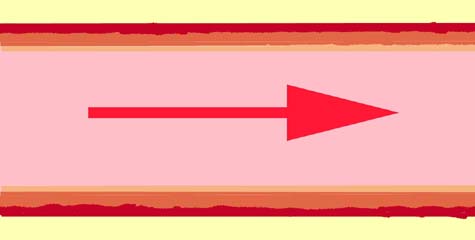
では、どうしたらよいのでしょうか?よく塩分制限を耳にします。塩分を制限することによって、腎臓にもよい結果と作用しますし、また余分の水分が貯まらないためにも必要です。そして大切なことは、太らないことと、適度な運動を行うことです。昔は血圧が高いから運動はしてはいけないなどと言われていましたが、最近は運動療法は高血圧の大切な治療法の一つです。(他の合併症がある場合は運動制限される場合もありますので、必ず主治医に相談下さい)太らないためには、食事療法も大切です。結果として成人病や糖尿病の項目で話していた治療法と基本は同じであることがご理解できたと思います。それでもコントロールされない場合など内服加療を行いますが、内服で血圧が下がっても、自己判断で中止しますと再び上昇してきます。主治医と相談しつつ食事や運動療法の効果とあわせて判断しなくてはいけません。

高尿酸血症と言うより痛風と言った方が有名かもしれません。この痛風は、血液中の尿酸という物質が高値になり、やがて尿酸結晶となって関節などに蓄積して炎症を引き起こして激しい痛みを生じるものです。しかし尿酸が高値でも痛風を生じにくい人もいますが、高尿酸血症が持続すると痛風という症状のみでなく、腎臓などにいろんな障害を引き起こします。尿酸は食事のみが原因でなく体内でも作られています。この尿酸を正常に排出するために、なるべく尿をアルカリ性にした方がよいのです。このため野菜繊維類などを食し、また尿量をいつも保つ必要があり、特に尿酸値の高い人は一日に2リットル(少なくとも1.5リットル)の水を飲むべきと言われています。最近は尿をアルカリに傾けるためのお薬もあり痛風予防に使われています。
血液中の尿酸値は、変動します。一度尿酸が高くても再検すべきでしょう。逆に一度低いから大丈夫とも言えません。いずれにしても年に1~2回は検査すべきです。また血液中の尿酸は運動や食事の影響を受けて上下します。痛風発作が生じるときは、血中の尿酸値が急激に変動したときが多いと言われ、運動後などに痛風発作が生じるのもこのためでしょう。
高尿酸血症の方は、ついつい痛風の予防や痛風の対処を考えます。自覚症状が強い痛風には誰でも敏感なのです。しかし高尿酸血症そのものが体にとってよくありません。糖尿病や高脂血症などと同様、症状がないときにこそ尿酸値を気にしてほしいのです。
タイトルには、高脂血症と書いていますが、近年脂質異常症と言います。(ここでは高脂血症のまままとめます)高脂血症と言っても実際にはどんな脂肪が高いかによって異なります。代表的なものがコレステロールと中性脂肪(トリグリセライド)です。そしてコレステロールには動脈硬化を抑制してくれる善玉コレステロールであるHDLーコレステロールと動脈硬化を促進させる悪玉コレステロールであるLDLーコレステロールがあります。ここまでは皆さんよくご存じでしょう。知ってみえる方は、これに過酸化脂質という言葉もあわせて動脈硬化に対してどのように悪影響を及ぼすかと言うこともご存知かもしれません。しかしここではそんな詳しい内容より、より具体的なことを書きます。
まずコレステロールは体にとって大切な成分の一つであることは間違いありません。ステロイドホルモンなどはコレステロールから合成され、人が健康でいられるため必要不可欠です。コレステロールは食事のみでなく体内でも合成されています。しかしここで問題があります。一つは過剰にコレステロールを摂取する場合ともう一つは体内で過剰にコレステロールを作ってしまう場合です。もちろん作られたコレステロールが体にとってよい働きのみしてくれれば良いのですが、そうは行きません。余分な悪玉コレステロールが存在し他のいろんな条件が加わるとこれが動脈硬化の原因となるのです。体質的にコレステロールが高い人を家族性高脂血症と言い、高い成分によって数種類に分類されています。次に述べる中性脂肪が高くなる家族性のものもあります。いずれにしてもこう言った人の中には早期に動脈硬化が進行し若くして心筋梗塞などを生じる場合もあります。それに対して普通の高コレステロール血症というのは、食事や運動が直接関係してきます。体内で作られるコレステロールも、運動によって抑えられたり、善玉コレステロールが増える作用もあります。食事ではコレステロールを多く含む食べ物は避けたいものです(近年食事の影響よりも体質の方が更に重要とされている)。
体に入ったカロリーは、結果的には中性脂肪として蓄えられます。ですから糖分やアルコールなどの摂取は直接中性脂肪の値にはね返ってきます。しかしこれも家族性があることは既にお話ししました。中性脂肪は脂肪肝などの原因となると言われていましたが、近年は動脈硬化とも密接な関係があることがわかり、当然動脈硬化を抑えるため高中性脂肪血症にも指導を行っています。食事と運動が基本であることは同じです。
最近は中性脂肪もコレステロールも良いお薬が開発され、内服によってコントロールできるようになりました。事実こう言ったお薬を用いることによって心筋梗塞の発症を抑え、結果的に死亡率を下げることも可能となってきています。どうか高脂血症を指摘されたのであれば、放置せず食事や運動療法を取り入れて、それでも改善しない場合は医師に相談して、少しでも恐ろしい合併症の発症を予防しましょう。
脂肪肝。フォアグラなら美味しそうですが、この名前で聞くと成人病の代表と言うイメージが浮かびます。これは肝臓の細胞の間に脂肪が沈着して徐々に肝細胞を障害する状態です。健康診断にて肝機能が悪いと言われました。そう言う中年男性の多くはこの脂肪肝です。では、脂肪肝はなぜいけないのでしょうか?将来肝硬変にでもなってしまうのでしょうか?実は、そう言った恐ろしさは少なく、実際には成人病である高脂血症、糖尿病、高尿酸血症、肥満、運動不足などと密接な関係があるため注意されるのです。つまり脂肪肝というのは、成人病の象徴のような状態なのです。
脂肪肝は、詳細は除きますが、常に血液中のインスリンが高値を示す高インスリン血症とも関連が深く、この高インスリン血症は極めて動脈硬化性の疾患を生じやすくなります。内臓肥満と言われる状態も同じことが言われています。内臓肥満は、皮下に脂肪分が沈着するタイプと異なり明らかに動脈硬化が進行します。欧米ではウエストとヒップの比をもってこの内臓肥満と皮下肥満と同じ分類を行っています。
皮下肥満に比べ内臓肥満は、お腹の中に、黒く見える脂肪がたっぷりと・・・
もちろん、内臓肥満のほうが動脈硬化などが早く進行すると言われています。少し話がそれましたが、脂肪肝は肝臓の障害のみで考えるのでなく、成人病への一つの兆候として考え、これまで何度も出てきた、食事療法運動療法をもう一度考え直すきっかけとしていただきたいのです。
(健康診断を行っている立場から考えて)
まず始めに、生活習慣病検診を行っている側についてお話しいたしましょう。最近は、コンピューターで検査結果を総合的に判断し、コメントでさえ、コンピューターが打ち出す健診が増えています。仮に同じ程度の肥満傾向の人が、共に軽度肝障害と尿酸値の上昇、そしてコレステロールの増加が見られ、更に二人とも胃透視検査で胃角部に不整があったとすると、この両者には全く同じコメントが打ち出され、しかも二次検査項目も全く同じとなります。それでも異常を見つけだすという健康診断に問題はありません。健康診断と言うのは、行う立場から言えば異常を見落とさないことが重要なのです。ごく軽度の肝機能障害でも障害は障害です。昨年まで正常であった人と昨年も同じように異常があったとしても、今年のこの検査で異常があれば、それは指摘しなければならないのです。また疑わしきは、全て二次検査というのが鉄則です。たぶん異常はないだろうが念のためと言う判定が多いのも事実です。しかしだからといって異常を放置して良いと言っているのではありません。残念ながら現在の一次健康診断は、健康診断そのものを行うソフトとハードはそろっていますが、その結果を個人に還元して説明したり、適切な二次検査の指導をするソフトもハードも不足していると言うことです。もしあなたが、かかりつけ医を持っていたら、そんな時こそ健康診断結果を持って受診し、ゆっくりと説明してもらって下さい。
(身長、体重、肥満度)
身長や体重ほど変動的なものはありません。しかし急激な体重増加や減少は疾患の存在を考えたり、あるいは疾患を引き起こす原因となります。最近は肥満度のみならず、体脂肪率も口にされますが、健康のために標準に維持するのが良いに決まっています。しかし体格というものは個人差があり、まず大切なことは、その人にとって今の状態が良いか悪いかを判断することでしょう。
(心電図、胸部レントゲン)
心電図は、電気的に心臓の動きや位置、電気の伝わり方を見ている検査です。大切な検査ですが一部の異常を除き、これのみで確定できる訳ではありません。他のレントゲンや二次検査で行う心エコーなどが必要な場合もあります。レントゲンは心臓と肺を中心に見ていますが、時に骨や縦隔と言う場所も見ています。大切な点は本来立体的な人の体を二次元的に見ているわけであり、これのみで異常が全て捕まるわけでないと言うことです。早期の肺癌を見つけるのには、無意味という意見もあります。しかしレントゲンに異常があれば二次検査をすべきであり、その意味では重要な検査です。
(一般血球検査あるいは一般血液、一般検血検査)
呼ばれ方がいろいろありますが、血液に含まれる赤血球や白血球、血小板の数や大きさ、容積、濃度を見ているものです。貧血の有無、血液増多、白血球異常、血小板異常を見つけるのみならず、種々の疾患のスクリーニングとして重要です。逆にこれのみで直接診断が付く疾患は少ないと言ってもいいでしょう。
(肝機能検査)
肝機能検査として、GOT、GPT、LDH、γ-GTP、ALP、ZTT、TTT、T-ビリルビンなどが有名です。GOTやGPTは、肝臓の細胞が壊れる時血液中に放出されるもので、上昇は多くの肝細胞が障害を受けている訳です。脂肪肝などでこれらが100は越えないがいつも上昇していると言う人は多いでしょう。LDHは肝臓に特異的なものではありません。しかし肝細胞の障害でも上昇します。γ-GTPとALPは胆道系を示します。と言っても難しいですが、γ-GTPは、俗に酒飲みの酵素と言われ、アルコール量が増えると上昇する人が多いです。もちろん両者とも他の疾患でも異常を来すわけですから、一度は二次検査が必要でしょう。ZTTやTTTなどは、健診としては大きな意味が無いとも言えます。慢性の炎症などで上昇しますが、その他の機序もあり参考にされることが少ないとも言えます。T-ビリルビンは総ビリルビンの略で、いわゆる黄疸の元になる物質の量を見ています。さて実際に良く問題とされるのは、GOT、GPT、γ-GTPではないでしょうか? まず以前にC型肝炎、B型肝炎の検査をして、しかも腹部超音波検査などで画像上腫瘍や慢性炎症所見もなく、仮に所見があっても脂肪肝のみであり、ここ数年肝機能異常を指摘されてもごく軽度。そしてその値に変化がない人の場合、放置して良いとは言いませんが、アルコールを含めた食事や運動指導はじめ生活改善以外方法がないことが多いです。但しその他に高脂血症や高尿酸血症などがあれば話は別です。
(脂質検査)
脂質検査は、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪が一般的です。まずこの検査を空腹時に行ったか否かを思い出して下さい。もしあなたが空腹時に行っていなければ、正しい指導は不可能です。食事によって値が変動する可能性が高いからです。この場合できたら空腹で再検しましょう。そしてやっぱり高値であれば、いわゆる高脂血症として指導を受けるべきです。上記の項目高脂血症を参照下さい。
(尿酸検査)
今回初めて尿酸値の上昇を指摘された方は、もう一度再検してみた方がよいでしょう。と言うのは、尿酸値は食事ばかりでなく前日の運動などにも左右されるからです。その上でやはり高値であった。とか昨年よりもまた少し上昇した。とか既に痛風発作の経験があると言う方は、こちらを参照下さい。
(血糖血、グリコヘモグロビンA1c検査)
血糖値は空腹時に検査したか否かを思い出し、空腹でなかったら再検して下さい。グリコヘモグロビンA1cも厳密には空腹の方がよいのですが、大きな影響でないのでそのまま話を続けます。まずグリコヘモグロビンA1cは、ほぼ40日間の平均の血糖値に比例します。したがってこれが高値と言うことは糖尿病の可能性が極めて高くなります。但し貧血などの他の要素で異常値が出る場合があるので、確定診断とは言えません。血糖値は変動が激しいため、ワンポイントの測定のみで判定するのは難しいのです。それでも全くの空腹で130mg/dlであれば糖尿病の可能性が高くなります。
(腎機能検査)
クレアチニン、尿素窒素と言うのがそうです。その他各電解質なども腎機能に含まれます。腎機能で注意が必要なことは、尿素窒素は変動する可能性が高いのに対して、クレアチニンは異常であればまず異常と言うことです。正常が~1.3となっていて、1.4なら「まーいいや」とは行きません。男女でも筋肉量でもその値は異なります。近年はeGFRを計算で求めて記載されていることも多いですから、少なくとも異常値に近いようであれば、たとえ正常範囲でも一度お医者さんに相談してください。
(胃透視や腹部超音波検査)
ここで異常を指摘されている場合、それはある医師や検査技師が異常ありと判断したものであるため、第三者が推測してその結果を評価することが難しいと言うことを知っていて下さい。ですから念のため胃カメラと、コメントされていた場合、5分5分で異常を疑うのか、2分8分で心配ないのか・・・と言うことがわからないのです。しかし冒頭でも書いたように異常は異常です。見落とさないと言うためにも二次検査を受けるべきでしょう。
(メタボリック症候群について)
いきなりですが、まずはメタボリック症候群の診断基準を示します。
腹腔内脂肪蓄積 ウエスト周囲径(お臍の部分で測定) 男性≧85cm 女性≧90cm
(内蔵脂肪面積換算で男女とも≧100㎠ に相当します)
上記に加えて以下のうち2項目以上満たせばメタボリック症候群と診断
脂質代謝異常 高トリグリセリド血症(高TG血症) ≧150mg/dl
かつ/または
低HDLコレステロール血症 <40mg/dl (男女とも)高血圧 収縮期血圧 ≧130mmHg
かつ/または
拡張期血圧 ≧85mmHg高血糖 空腹時血糖 ≧110mg/dl
いかがですか?
ウエスト周囲と言っても、お臍の上で測定してください。しかも締め付けずに正確に測ってください。これは脂肪肝の項目でも紹介しました内蔵脂肪の蓄積量を推定するのに用います。実際にはCTを用いて測ったりしますが、これまでの数多くの医学的検討からこの腹囲を測ることで一定以上の内蔵脂肪の蓄積がわかることが実証され、これを用いています。
下の3つの項目は一般的な健康診断でも行われる検査ですが、このうち2つ以上満たせば、メタボリック症候群と診断されます。
【メタボリック症候群の意味】
シンドロームXとか、突然死症候群などと言われ、一昔前まで比較的若くして心筋梗塞などで命を失う人たちを注意してきましたが、実はこの方々と同様の病態が実際には多く認められ、動脈硬化が同年代の人たちよりも早く進むことが知られてきました。そしてそう言った方々を検査追求して一つの概念が提唱されてきました。これがメタボリック症候群です。
つまりメタボリック症候群とは、同年代の人たちよりも動脈硬化性疾患を引き起こし、種々の生活習慣病、及びそれに伴う合併症の危険性が高く、更に突然死なども生じやすい状態を指摘するために提唱されるようになった概念なのです。
【動脈硬化とは】
動脈硬化とは血管が固くなる・・・と言う意味に解釈されがちですが、少し違います。もちろん最終的に石灰化を生じて血管が卵の殻のように硬くなることもありますが、ここで指摘する動脈硬化とはコレステロールなどの沈着によって血管の中にプラークが貯まり、それが破裂することによって生じる血栓、そしてその血栓によって重要な動脈が閉塞することが引き起こす重篤な疾患が問題となると言う意味の動脈硬化なのです。
【どうしたらよいのか?】
・まずは減量です。つまり内蔵脂肪を減らすことが重要です。内蔵脂肪は過剰なカロリー摂取などによって蓄積しやすいですが、逆に皮下脂肪に比較して燃焼させやすいこともわかっています。ですから単純にイン・アウトの関係を考え、カロリーの取りすぎに注意します。と書くのは簡単ですが、これが一番難しいです。ですからここではあえて極端な指導を書きます。(実際の実施には主治医にご相談下さい)
①食事前に必ずお茶を一杯飲む ②口に入れた食べ物は10回以上必ず噛む ③朝、昼、夕を規則正しくする ④油ものを極力避ける ⑤アルコールはビール350ml、ウイスキー水割り2杯、焼酎・酒1合までとし、ご飯どんぶり一杯分のカロリーと同じだと認識する ⑥食事摂取中もできるだけお茶や水を飲む
以上が極端ですが私からの提案です。
・次に運動です。運動というと若い人ほど筋肉トレーニングをイメージし、ダンベルや腕立て、腹筋をされますが、ここでお勧めしているのはエアロビックな運動です。ウオーキング、ジョッギング、自転車(エアロバイク)、ステップ、ダンス、水泳、水中歩行などです。
またエアロバイクなどでは消費カロリーが表示されたりします。40分もやったのに消費カロリーは400カロリー以下・・・なんてこともあります。しかし間違わないでください。運動はカロリー消費のために行うのではありません。食べ過ぎた分を消費すると言う発想は捨ててください。食事療法でのカロリーを控えない限りダイエットはほとんど不可能です。
なぜ運動するかというと、細胞内での新陳代謝の活性化やインスリン感受性の上昇が期待されるからです。わかりにくいでしょうからここでも極端な表現を使って書きます(医学的説明としては妥当ではありません)と、運動を取り入れると、太りにくくなる!ってことです。もちろん上で書いたように運動しても食事療法が守られなければ改善しません。しかしエアロビック運動を続けていると前と同じ食事でも必ず前より太りにくくなっているはずです。
【高脂血症、高血圧、糖尿病を放置しない】
このページの別の項目、生活習慣病の中で全て取り上げている名前です。これらの特徴は、自覚症状がないってことです。
ですから、せっかく健康診断でこのことがわかっていても何ともないから・・・なんて言って放置されているのです。しかし実際には確実に動脈硬化は進んでいきます。そしてある時牙をむきます。心筋梗塞による突然死、脳卒中による半身不随・・・・・ そうなってからでは遅いのです。
内蔵脂肪を減らせるのと同時にこの以上についても積極的治療が必要です。上に示した食事や運動療法を行うことでこれらも改善する可能性もあります。しかし確実に改善させるためには気心の知れた何でも相談できる親身になっていただける主治医を持つことです。
さあーメタボリック症候群の診断にマッチされていた方は、すぐにでも取り組んでください。
それが、今後のあなたの合併症を予防する大切な一歩となるはずです。
![]()